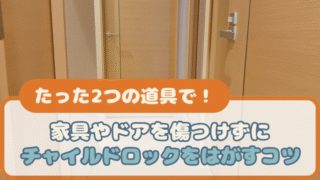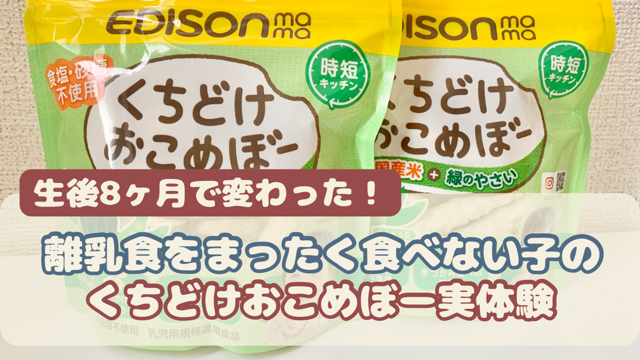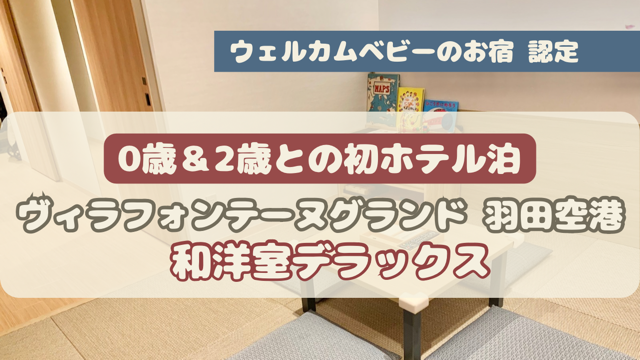幼い子どもや赤ちゃんとの引越しは準備だけでも本当に大変ですよね。
日々の育児に加えて、物件の内覧、荷造りや住所変更の手続き…
実際に私は、上の子が1歳、下の子が生後4ヶ月という時期に東京23区で引越しを経験しました。
当時は時間がなかったので、とにかく「効率重視」で準備を進めました。
この記事では、私の実体験を元に赤ちゃん連れの引越しをスムーズに進めるための具体的なコツを公開しています。
- 赤ちゃん・子連れで引越し準備を効率的に進めるコツ
- 赤ちゃん・子連れで実際に引越した当日の流れと注意点
- 忙しいママ・パパに役立つ便利な引越しサービス
この記事を読めばきっと、赤ちゃん連れでも効率的に引越し準備を進めるためのヒントが得られますよ。
引越しを控えているママ・パパに安心感を与えられたら嬉しいです。
なお、チャイルドロックを綺麗に剥がす方法については、別記事「家具やドアを傷つけずにチャイルドロックを剥がすコツ」で詳しく紹介しています。
赤ちゃん・子連れ引越し|事前準備を段取りよく進めることが大切

赤ちゃん連れの引越しは、早めに準備を進めて時間に余裕を持たせることが何より大切です。
大人だけの引越しと違って赤ちゃんの授乳やお昼寝、機嫌の波など生活リズムを優先する場面が多いです。
そのため、準備を段取りよく計画的に進めることが重要です。
- 業者とのやり取りはメール中心にする
- 引越し見積もり対象になるベビー用品をチェックする
- 引越し時の不用品回収は早めに手配する
- 引越しの荷造りはコツコツ進める
- 引越し当日の冷蔵不要の食事を準備しておく
ポイント1:引越し業者や不動産会社とのやり取りはメール中心に

特に0歳児がいると、お世話で手が離せず電話に出られないことが多いです。
私は実際に、不動産屋の担当者に事情を説明してなるべくメールでのやり取りをお願いしました。
また、メールなら内容を確認しやすく、記録として残るため後で振り返る際にも便利です。
一方で、返信が遅れると契約などの手続きに影響が出てしまうこともあります。
そのため私は、要点だけは先に電話で伝えておくなどして、手続きに支障が出ないように工夫しました。
ポイント2:引越し見積もり対象になるベビー用品をチェック

引越しの見積もり料金シミュレーションにはベビー用品は含まれていないことが多いです。
そのため、事前にこれらも含めて見積もりしてもらうように念押ししておくことが大切です。
我が家で実際に見積もり依頼に含めたベビー用品は以下のとおりです。
大型のベビー用品はかさばるため、あらかじめ引越し業者に伝えておかないとトラブルになりかねません。
また、不要となって処分したベビー用品もありました。
ポイント3:引越し時の不用品回収は早めに手配

子どもの成長で不要になったものに加えて、新居に合わない家具や収納用品など、不用品は想像以上に多く出ます。
実際に我が家では、古い家電や自転車、衣装ケース、小さな棚などを合わせると軽トラック一台がいっぱいになりました。

自分たちで部屋から運び出すだけでも大変なので、不用品回収業者に依頼するのがおすすめです。
ポイント4:引越しの荷造りはコツコツ進める
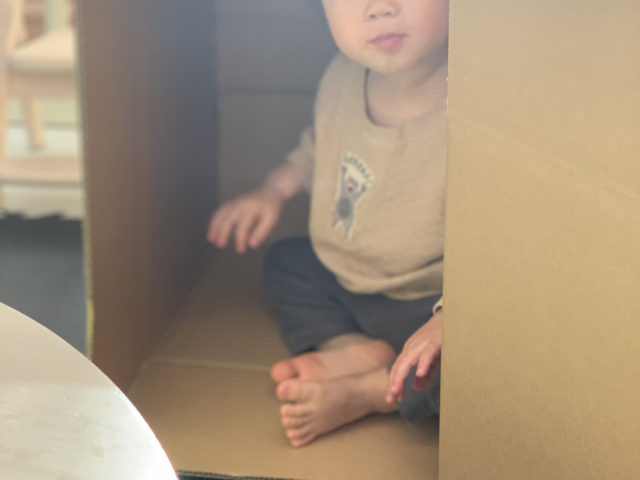
子どもの相手をしながらの荷造りは、とにかく時間との戦いです。
- 子どもが遊ぶ用の段ボールを用意する
- 荷造りに使うペンはノック式にする
我が家では、段ボールを大小合わせて40枚ほど使いましたが、その様子を見た1歳の上の子が遊び始めてしまいました。
そのため、事前に遊び用の段ボールを1〜2箱組み立てて子どもに渡しておくのがおすすめです。
実際に、子どもが遊んでいる間に荷造りを進めることができました。
また、荷造りに使うペンはノック式がとても便利です。

キャップ式だと子どもがキャップを外したり、なくしたりすることもありますが、ノック式はその心配がありません。
ゼブラ 油性マーカー マッキーノック 太字 黒3本入 P-YYSB6-BK3-AZ
ポイント5:引越し当日用に冷蔵不要の食事を準備

引越しの前日には冷蔵庫の水抜きのため、コンセントを抜いておく必要があります。
そのため、引越し当日の朝ご飯やお昼ご飯は冷蔵不要のものを準備しました。
1歳の上の子には、おにぎりやバナナなど手軽に食べられるものを用意しました。
また、洗い物が出ないように紙皿や紙コップ、割り箸も活用しました。
赤ちゃん・子連れ引越し|当日の作業は工夫を取り入れ効率化する

赤ちゃんや小さな子がいると、引越し当日は思うように動けないことが多いです。
我が家で実際に行った工夫を4つ紹介します。
- 転居元の引き渡し日を伸ばす
- 新居の間取り図を印刷しておく
- 引越し当日の助っ人を呼ぶ
- 引越しのタイムスケジュールを組む
工夫1:転居元の引き渡し日は余裕を持たせる
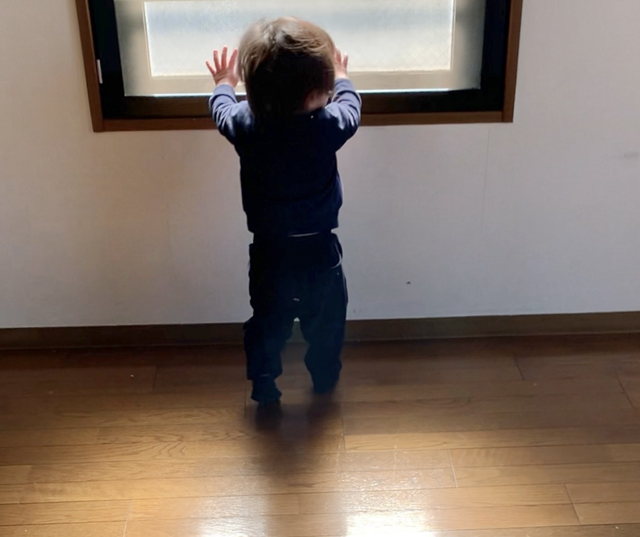
転居元の引き渡しを引越し日当日にするのは、赤ちゃんがいると負担がとても大きいです。
我が家の場合も、当日は1歳児が作業に興味津々で動き回り、0歳児は常に抱っこが必要な状態でした。
また、前日まで荷造りに追われて疲れも溜まっていました。
そのため、家賃が多少かかっても引き渡し日は1週間程度延ばしておくのがおすすめです。
引越しの翌日以降に予定しておくと、時間に余裕を持って対応ができます。
- 転居元の室内の掃除
- 不用品回収やゴミ出し
- ガス・電気・水道など停止立ち合い
実際に我が家では、転居元に関わる作業は引越し後1週間かけて実施しました。
工夫2:新居の間取り図を印刷しておく

新居の間取り図を印刷しておくと、引越し業者への搬入指示が格段にスムーズになります。
実際に我が家では、A4用紙に2〜3枚印刷して引越し作業員の方に渡しました。
すべて口頭で説明するよりも伝えやすく、家具や段ボールを効率よく運んでもらえました。
工夫3:引越し当日の助っ人を呼ぶ

赤ちゃんがいる引越しでは、当日サポートしてくれる人がいるだけで本当に助かります。
子どもの相手をしながら荷解きや搬入をするのは難しく、思うように作業が進まないことが多いからです。
我が家では、祖父母に来てもらい、子どもたちの相手を2時間ほどお願いしました。
その間に必要最低限の育児用品や寝具、風呂用品を優先して荷解きすることができました。
工夫4:引越しのタイムスケジュールを組む

引越し当日のタイムスケジュールを家族と共有しておくことで大きな安心につながります。
なお、我が家では特に子どもたちの食事や睡眠時間を意識してスケジュールを組みました。
- AM 2:00就寝
- AM 6:00起床・身支度
- AM 6:30朝食
- AM 7:00荷物の梱包・最終チェック
- AM 8:00荷物搬出開始
- AM 9:00荷物搬出終了
- AM 9:10旧居から新居へ移動
- AM 9:30荷物搬入開始
- AM 10:00荷物搬入終了
- AM 10:30祖父母が到着
- AM 11:00荷解き
- PM 1:00昼食
- PM 1:30お昼寝(上の子)
- PM 5:00夕食
- PM 7:00お風呂
- PM 8:00就寝(子ども)
- PM 10:00荷解き
- PM 11:00就寝
赤ちゃん・子連れ引越し|便利な引越しサービス紹介
赤ちゃんがいると、引越し業者を探したりやり取りするのもひと苦労です。
実際に、我が家の引越しスケジュールは入居日決定後から引越しまでは2ヶ月弱しかありませんでした。
- 12月末賃貸物件申込
- 1月賃貸契約完了
- 2月新居の内覧
- 3月引越し
- 4月旧居の精算完了
引越し業者を選ぶのにも、見積もり依頼、引越し日の空き状況の確認などやることが多いです。
そこで便利なのが複数の引越し業者を一括で比較できるサービスです。
その中でも、SUUMO引越し見積もりがおすすめです。
電話番号の入力が任意なので、見積もり依頼をしても電話対応をする必要はありません。
また、実際に引越し業者を利用した人の口コミ・評判も多数掲載されています。
- 厳選引越し会社から見積もり先を選べる
- 電話番号入力なしで見積もり可能
- 引越し料金が最大80%安くなる
赤ちゃん・子連れ引越し|子どもに関する住所変更リスト
実際に我が家で実施した、子どもに関する住所変更のリストです。
忘れないように、期限や手続き場所などはリスト化しておくことをおすすめします。
- 保育園の登録情報
- 支給認定証(保育の必要性の認定)
- 乳児医療証
- 子どもの健康保険証
- 子どもの銀行口座
- 子どものマイナンバーカード
- 子どもの保険
- オンライン診療の登録情報
- ベビーシッターの登録情報
- 東京都018サポート申請情報
まとめ
赤ちゃんや子どもと一緒の引越しは、思った以上に時間も手間もかかります。
だからこそ、事前に段取りよく準備を進め、当日は工夫やサポートを取り入れることが何より大切です。
我が家では、子ども2人のお世話をしながら約2か月かけて準備を行いました。
また、当日も祖父母に助けてもらうことで無事に引っ越しを終えることができました。
同じように幼い子を育てながら引っ越しを考えている方にとって、この記事が少しでも役に立てば嬉しいです。
読んでいただきありがとうございました。